
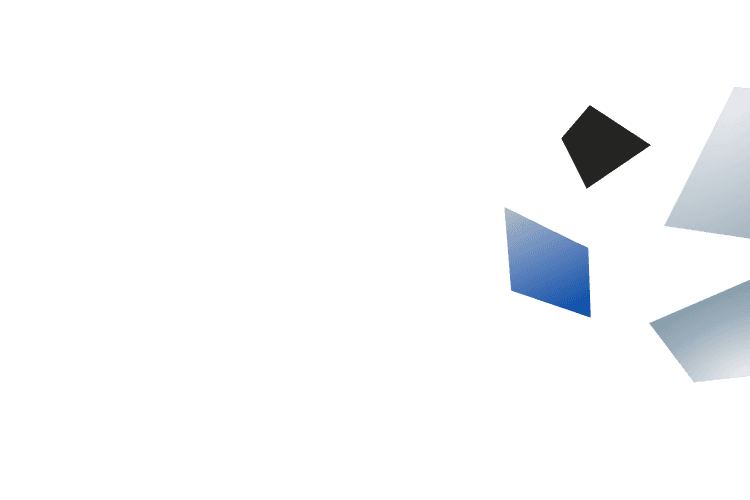
No.01
のぞむは明か時




相原は暢気な様子であった。
富山行きの北陸新幹線の車内、駅で買った弁当を口に運びつつ、咀嚼とともに知り合いの経営者の言葉を薄く反芻する。まだ暖かくなりきらない気温を感じさせるひやりとした車窓からの景色は、普段の通勤時のそれとは違う緑の多さで、自分が今東京から離れていっていることを実感させた。
「知り合いにECサイトを作ってほしいという人がいる」と、経営者の友人である大村に話をされてから、この新幹線に乗るまで、それほど時間はかからなかった。ちょうど富山に行くという大村の予定に合わせ、行ったことのない土地へ遊びがてらついて行く。顔を合わせるのは知らない会社の知らない社長絵はあるものの、それくらいの感覚だったのだ。 肝心の同行人は、今は同じ新幹線で口を開いて寝ている。
大村から紹介されたその人は、食品製造・流通会社の三代目社長だという。経営70年目ということもあり、地元ではかなり大きく、言うなれば目立っている企業だった。
暢気でいられるのにも理由があった。昔ながらの大きい企業が、東京のベンチャー企業とタッグを組んでデジタルの領域に進んでいくというのは、ちょっと新しいことを始めたい。先代とは違うことに挑戦してみたい。そういった類の簡単なものだろうと考えてしまっていたのだ。
空の弁当箱と散らばった割り箸を乱雑にビニール袋へ詰め入れ、到着のアナウンスをBGMに、軽い腰を上げる。降り立ったその人口的かつ無機質な駅に見慣れたものを感じながら、東京にはない空気を吸い込んだ。
宿泊するホテルに荷物を置き、身軽になった体を伸ばす。足取りは重くもなく、向かった会食の場は地元の海鮮を扱った創作料理の料亭だった。料亭、とは言えど想像より堅苦しくはなく、カジュアルで落ち着きのある雰囲気のこの店は、これから対面する社長の選択だという。
かまくらのようなドーム型の個室に案内され、緊張なのか不安なのかわかりにくい胸の動悸が、ほんの少し、感じられた。
この動悸の訳を探る間も無く目が合ったその人は、威厳が漂うまっすぐな姿勢で座っていた。銀で縁取られた眼鏡越しの目は、明らかに相原のビビットな緑色の髪に目を向けている。
澤田と名乗るその社長は、思っていた通りの、オーラのあるまるで「殿下」のような風貌だ。
富山の魚は美味い。ホタルイカは苦手だったが、ここの沖漬けは追加を頼んでしまうほどに美味だ。うまいうまいと連呼しながらも、相手のことを探っていた。それはきっと互いにであろう。というのも澤田は、相原よりも前に紹介をしてもらっていた会社で失敗をした経験があった。前と同じような失敗は繰り返してはならない、見定めなくては、そういった気持ちが拭いきれずにいたのだ。
一方相原は、澤田のことをわかりきれていなかった。
というのも、食品流通の大企業の社長がどんな商品を売り出すのかと話を聞いていると、聞き間違いかという単語が端的に出てきたからだ。
「沼です」
料理に箸を運ぶ手がわかりやすく止まり、ただその単語を反復するしかなかった。
「沼、ですか?」
見た目にはあまり食事とは思えない、激しいトレーニングで鍛え抜く人々のためのお粥のような栄養食のことだという。思い付きなのかどうか疑ってしまうような商品だったが、澤田が取り出したのは、百ページはあるであろう分厚い資料だった。その資料は澤田自身が考え、月日が変われど調べ尽くし、作成したものであるということに、相原はますますわからなくなったのだ。
こんな量を調べ、学び、資料を作る時間はどこにあるのか?一般的にこういうものは部下に任せるのではないか?もしかしたら、自分が思う以上に真面目で、そしてこの「沼」に対して本気なのか?この「沼」は売れるのか?
ホタルイカの沖漬けに箸を伸ばしながらも、理解を追いつかせようとしていた。
料理も終盤に差し掛かった頃、澤田はペースの落ちた咀嚼を終え、一言付け加えるかのように零した。
「そういえば。工場、もう作っちゃってるんですよねえ」
富山行きの北陸新幹線の車内、駅で買った弁当を口に運びつつ、咀嚼とともに知り合いの経営者の言葉を薄く反芻する。まだ暖かくなりきらない気温を感じさせるひやりとした車窓からの景色は、普段の通勤時のそれとは違う緑の多さで、自分が今東京から離れていっていることを実感させた。
「知り合いにECサイトを作ってほしいという人がいる」と、経営者の友人である大村に話をされてから、この新幹線に乗るまで、それほど時間はかからなかった。ちょうど富山に行くという大村の予定に合わせ、行ったことのない土地へ遊びがてらついて行く。顔を合わせるのは知らない会社の知らない社長絵はあるものの、それくらいの感覚だったのだ。 肝心の同行人は、今は同じ新幹線で口を開いて寝ている。
大村から紹介されたその人は、食品製造・流通会社の三代目社長だという。経営70年目ということもあり、地元ではかなり大きく、言うなれば目立っている企業だった。
暢気でいられるのにも理由があった。昔ながらの大きい企業が、東京のベンチャー企業とタッグを組んでデジタルの領域に進んでいくというのは、ちょっと新しいことを始めたい。先代とは違うことに挑戦してみたい。そういった類の簡単なものだろうと考えてしまっていたのだ。
空の弁当箱と散らばった割り箸を乱雑にビニール袋へ詰め入れ、到着のアナウンスをBGMに、軽い腰を上げる。降り立ったその人口的かつ無機質な駅に見慣れたものを感じながら、東京にはない空気を吸い込んだ。
宿泊するホテルに荷物を置き、身軽になった体を伸ばす。足取りは重くもなく、向かった会食の場は地元の海鮮を扱った創作料理の料亭だった。料亭、とは言えど想像より堅苦しくはなく、カジュアルで落ち着きのある雰囲気のこの店は、これから対面する社長の選択だという。
かまくらのようなドーム型の個室に案内され、緊張なのか不安なのかわかりにくい胸の動悸が、ほんの少し、感じられた。
この動悸の訳を探る間も無く目が合ったその人は、威厳が漂うまっすぐな姿勢で座っていた。銀で縁取られた眼鏡越しの目は、明らかに相原のビビットな緑色の髪に目を向けている。
澤田と名乗るその社長は、思っていた通りの、オーラのあるまるで「殿下」のような風貌だ。
富山の魚は美味い。ホタルイカは苦手だったが、ここの沖漬けは追加を頼んでしまうほどに美味だ。うまいうまいと連呼しながらも、相手のことを探っていた。それはきっと互いにであろう。というのも澤田は、相原よりも前に紹介をしてもらっていた会社で失敗をした経験があった。前と同じような失敗は繰り返してはならない、見定めなくては、そういった気持ちが拭いきれずにいたのだ。
一方相原は、澤田のことをわかりきれていなかった。
というのも、食品流通の大企業の社長がどんな商品を売り出すのかと話を聞いていると、聞き間違いかという単語が端的に出てきたからだ。
「沼です」
料理に箸を運ぶ手がわかりやすく止まり、ただその単語を反復するしかなかった。
「沼、ですか?」
見た目にはあまり食事とは思えない、激しいトレーニングで鍛え抜く人々のためのお粥のような栄養食のことだという。思い付きなのかどうか疑ってしまうような商品だったが、澤田が取り出したのは、百ページはあるであろう分厚い資料だった。その資料は澤田自身が考え、月日が変われど調べ尽くし、作成したものであるということに、相原はますますわからなくなったのだ。
こんな量を調べ、学び、資料を作る時間はどこにあるのか?一般的にこういうものは部下に任せるのではないか?もしかしたら、自分が思う以上に真面目で、そしてこの「沼」に対して本気なのか?この「沼」は売れるのか?
ホタルイカの沖漬けに箸を伸ばしながらも、理解を追いつかせようとしていた。
料理も終盤に差し掛かった頃、澤田はペースの落ちた咀嚼を終え、一言付け加えるかのように零した。
「そういえば。工場、もう作っちゃってるんですよねえ」
富山の街を照らす街灯は、宿泊するホテルへの帰路の大村と相原の顔も薄く照らしている。
「大村くん、どこまで本気なの?」コンクリートの影の上を歩く二人の会話は、先ほどの会食でのことだった。
「だって、今からネットで売り始めるのって、そんな簡単じゃないだろ。」
相原には、自信がなかった。当初考えていたのは、単なるECの製作であった。しかし話を聞いてみると、初の自社商品を、社運をかけチャレンジをするほどの大きな取り組みであった。
もし本当にこの案件を進めるとすれば、相当大きなプロジェクトになるだろう。メーカーとして初めてデジタルの領域に足を踏み入れる会社となると、価格やSKUなどプロダクト設計、Web全般の整備、マーケティングからSNSなど何からなにまでやるべき事は途方もない。
だがあの膨大な資料や勉強量、熱意のある説明、すでに作っている工場。本気であることに疑いはもうない。そして、全てを任されるようなプロジェクトを想像すれば、面白いとさえ思う自分もいたのだ。
不安と興味は共存し得るらしい。
「実は提案で別の会社も入っているんだ。それでも僕は相原さんを信頼しているし、君にこの仕事を任せたい。」と言う大村の目は、相原の高揚感を後押しした。
相原の抱いていた少々の不安は、消えてはいなかった。膨大な資料を見ても、あの商品をどうしたら売ることができるのか、想像できないのだ。
「少し考えさせてほしい」の返事を聞いた大村は、大きく頷いてはいなかったが、翌日まで猶予をくれた。相原はホテルの大浴場のサウナに少しの疲弊が溜まった体を委ね、巡る思考を整理していた。吹き出るような汗と同じくらいの問題点や不安要素を、一つ一つ潰していくように。
少々浅い睡眠だったのは、絡まっていた思考によるものか、それともホテルのベッド特有の硬さによるものか。
大村と合流し向かう喫茶店までの道中、特に目立った会話はなかった。大村が結論に触れてこないのは、ある程度理解をしていたからだろう。
到着した味のある喫茶店には、夫婦であろうウエイトレスと、マスター、数名の客、奥には相変わらずのオーラの社長が座っている。少し廃れたワインレッドの色のソファ席に腰をかけ、挨拶を交わす。昨晩の挨拶とは雰囲気の違う、濁りの漂わない空気だった。この時点で、相原はこの契約がどうなるかを感じ取っていた。
アイスコーヒーとオレンジジュースを同時に頼む相原に少々笑っていた澤田だったが、運ばれたアイスコーヒーを、開ききらない目を覚ますため一気に飲み干す相原にはさすがに吃驚した様子であった。時間をかけて抽出したコーヒーをこうもすぐ飲み干されるとは、マスターも予想はしていないだろう。
数秒の間が心地よくすぎた頃、澤田が口を開いた。
「相原さんとこにするよ、俺」
オレンジジュースに手を移す相原に、澤田は変わらない調子で話した。相原と同じように、昨晩は考え込んだのだろう。
相原がさほど驚かなかったのは、相原自身も心に決めていたからだ。金額面や相当な時間や労力を要するであろうこと、全てを話した上でも澤田の覚悟を感じていたのが大きな理由だった。
自分も本気でやるしかない。そう思った相原と澤田の握手は、一層強いものとなった。
一人で帰る新幹線の中、富山から一駅過ぎないうちに駅弁を食べ終えた相原は、車窓のくぼみに肘を置きながら考え込んでいた。
予算はどうしよう。メンバーは誰にしよう。いつから何を進めて、何から着手しよう。様々な数字や情報がごった返す相原の脳内に、一人の女性の顔が鮮明に浮かんでいた。
「大村くん、どこまで本気なの?」コンクリートの影の上を歩く二人の会話は、先ほどの会食でのことだった。
「だって、今からネットで売り始めるのって、そんな簡単じゃないだろ。」
相原には、自信がなかった。当初考えていたのは、単なるECの製作であった。しかし話を聞いてみると、初の自社商品を、社運をかけチャレンジをするほどの大きな取り組みであった。
もし本当にこの案件を進めるとすれば、相当大きなプロジェクトになるだろう。メーカーとして初めてデジタルの領域に足を踏み入れる会社となると、価格やSKUなどプロダクト設計、Web全般の整備、マーケティングからSNSなど何からなにまでやるべき事は途方もない。
だがあの膨大な資料や勉強量、熱意のある説明、すでに作っている工場。本気であることに疑いはもうない。そして、全てを任されるようなプロジェクトを想像すれば、面白いとさえ思う自分もいたのだ。
不安と興味は共存し得るらしい。
「実は提案で別の会社も入っているんだ。それでも僕は相原さんを信頼しているし、君にこの仕事を任せたい。」と言う大村の目は、相原の高揚感を後押しした。
相原の抱いていた少々の不安は、消えてはいなかった。膨大な資料を見ても、あの商品をどうしたら売ることができるのか、想像できないのだ。
「少し考えさせてほしい」の返事を聞いた大村は、大きく頷いてはいなかったが、翌日まで猶予をくれた。相原はホテルの大浴場のサウナに少しの疲弊が溜まった体を委ね、巡る思考を整理していた。吹き出るような汗と同じくらいの問題点や不安要素を、一つ一つ潰していくように。
少々浅い睡眠だったのは、絡まっていた思考によるものか、それともホテルのベッド特有の硬さによるものか。
大村と合流し向かう喫茶店までの道中、特に目立った会話はなかった。大村が結論に触れてこないのは、ある程度理解をしていたからだろう。
到着した味のある喫茶店には、夫婦であろうウエイトレスと、マスター、数名の客、奥には相変わらずのオーラの社長が座っている。少し廃れたワインレッドの色のソファ席に腰をかけ、挨拶を交わす。昨晩の挨拶とは雰囲気の違う、濁りの漂わない空気だった。この時点で、相原はこの契約がどうなるかを感じ取っていた。
アイスコーヒーとオレンジジュースを同時に頼む相原に少々笑っていた澤田だったが、運ばれたアイスコーヒーを、開ききらない目を覚ますため一気に飲み干す相原にはさすがに吃驚した様子であった。時間をかけて抽出したコーヒーをこうもすぐ飲み干されるとは、マスターも予想はしていないだろう。
数秒の間が心地よくすぎた頃、澤田が口を開いた。
「相原さんとこにするよ、俺」
オレンジジュースに手を移す相原に、澤田は変わらない調子で話した。相原と同じように、昨晩は考え込んだのだろう。
相原がさほど驚かなかったのは、相原自身も心に決めていたからだ。金額面や相当な時間や労力を要するであろうこと、全てを話した上でも澤田の覚悟を感じていたのが大きな理由だった。
自分も本気でやるしかない。そう思った相原と澤田の握手は、一層強いものとなった。
一人で帰る新幹線の中、富山から一駅過ぎないうちに駅弁を食べ終えた相原は、車窓のくぼみに肘を置きながら考え込んでいた。
予算はどうしよう。メンバーは誰にしよう。いつから何を進めて、何から着手しよう。様々な数字や情報がごった返す相原の脳内に、一人の女性の顔が鮮明に浮かんでいた。




吉岡はただ困惑していた。
相原の会社に入社する前、突然「手伝って欲しいプロジェクトがある」と、突然相原から電話で告げられていた。
入社後、少しずつプロジェクトに関わっているものの、前職との仕事の仕方が異なる部分が多くまだ慣れきっていなかった中で、電話で告げられていたとあるプロジェクトは動き始めたのだ。
話を聞けば、「沼」だとか、工場をもう作り始めているだとか、ターゲット層は過酷なトレーニングをする筋肉隆々な人だとかで、普段筋トレなど全くしない自分がどうクリエイティブに携わっていいか考えるほどわからなくなっていた。
相原は、吉岡の前職からの仕事ぶりやセンスを信頼し、ロゴやパッケージなどゼロから製作しなくてはいけないこの案件のクリエイティブにおける適任だと感じていたのだが、吉岡の不安はそこにもあった。
入社後の顔合わせでのメンバーに、Web制作以外のクリエイティブに対応している人がおらず、自分で段取りを踏み間違えたら多大な影響が周りにも出てくると感じていたからだ。
不安に思う要因は、その商品にもあった。競合を心配した吉岡がポジショニングマップを作成してみると、「ガチガチの筋トレをする人」といったターゲティングは、競合過多であることがわかり、ターゲティングとコンセプトの再考が必要となったのだ。
まだ慣れないオフィスの片隅で、数ある不安要素に意気消沈しているように見えたのだろうか。向かいの席にいたプロジェクトの広告関連のトップである林が、パソコンの画面越しに目を合わせて言った。
「僕たちがしっかり数字を見るので、吉岡さんはクリエイティブに集中してくれれば大丈夫ですよ」
柔らかいが芯のあるその声に安堵を覚え、このメンバーであれば大丈夫。そう思った。
吉岡は、澤田に向けたコンセプトとターゲットの再考提案のために、アンケートを取り始めていた。会社の社員、友人などに一般的な健康食品に対してのイメージを聞いて回ったのだ。
一般的な健康嗜好の料理には否定的な意見が多く、中でも「美味しくない」という意見が目立っていた。続けて購入されない原因はそこであろうと予想し、さらなるインサイトの理解のため、なおターゲットに近いジムへ通う人へインタビューを行った。
そうすると、「こってりしたものを避けて栄養摂取しているため、好きな味を我慢しないといけない」という意見があり、ヘルシーかつ、さっぱりしたものからこってりしているものまで、美味しく栄養が補助できる食品にニーズがあると、吉岡は推測した。
相原の会社に入社する前、突然「手伝って欲しいプロジェクトがある」と、突然相原から電話で告げられていた。
入社後、少しずつプロジェクトに関わっているものの、前職との仕事の仕方が異なる部分が多くまだ慣れきっていなかった中で、電話で告げられていたとあるプロジェクトは動き始めたのだ。
話を聞けば、「沼」だとか、工場をもう作り始めているだとか、ターゲット層は過酷なトレーニングをする筋肉隆々な人だとかで、普段筋トレなど全くしない自分がどうクリエイティブに携わっていいか考えるほどわからなくなっていた。
相原は、吉岡の前職からの仕事ぶりやセンスを信頼し、ロゴやパッケージなどゼロから製作しなくてはいけないこの案件のクリエイティブにおける適任だと感じていたのだが、吉岡の不安はそこにもあった。
入社後の顔合わせでのメンバーに、Web制作以外のクリエイティブに対応している人がおらず、自分で段取りを踏み間違えたら多大な影響が周りにも出てくると感じていたからだ。
不安に思う要因は、その商品にもあった。競合を心配した吉岡がポジショニングマップを作成してみると、「ガチガチの筋トレをする人」といったターゲティングは、競合過多であることがわかり、ターゲティングとコンセプトの再考が必要となったのだ。
まだ慣れないオフィスの片隅で、数ある不安要素に意気消沈しているように見えたのだろうか。向かいの席にいたプロジェクトの広告関連のトップである林が、パソコンの画面越しに目を合わせて言った。
「僕たちがしっかり数字を見るので、吉岡さんはクリエイティブに集中してくれれば大丈夫ですよ」
柔らかいが芯のあるその声に安堵を覚え、このメンバーであれば大丈夫。そう思った。
吉岡は、澤田に向けたコンセプトとターゲットの再考提案のために、アンケートを取り始めていた。会社の社員、友人などに一般的な健康食品に対してのイメージを聞いて回ったのだ。
一般的な健康嗜好の料理には否定的な意見が多く、中でも「美味しくない」という意見が目立っていた。続けて購入されない原因はそこであろうと予想し、さらなるインサイトの理解のため、なおターゲットに近いジムへ通う人へインタビューを行った。
そうすると、「こってりしたものを避けて栄養摂取しているため、好きな味を我慢しないといけない」という意見があり、ヘルシーかつ、さっぱりしたものからこってりしているものまで、美味しく栄養が補助できる食品にニーズがあると、吉岡は推測した。




どのニュースでも猛暑日の文字が並ぶほどの気温の中、都内のビル群のガラスは日光を反射し、ワイシャツを纏った会社員たちの歩くコンクリートを熱していた。
プロジェクトが始まってからというものの、季節を感じる間もないほどのスピード感で物事が進み、冷房が社内を冷やし始めたのもいつからだったか、記憶には薄い。
吉岡の集めたアンケート結果を持って、プロジェクトメンバーによるターゲティング再考の会議が行われた日は、無理矢理吐き出したような冷房の音がよく聞こえるほどに、主要メンバー五人の雰囲気は落ち着いていた。 各々自分の考えたターゲットを口にしている中で、「ランナー。」と吉岡が呟いた。この発案にも様々な理由が詰まっている。
まず一つに、次々と澤田の工場から送られてくる試作品の一品の量の満足感だった。いわゆるダイエッターに向けて満足感のあるものを売るのではなく、しっかりと食事の量を取りながらも消化や栄養面を気にかけるランナーにアプローチすることを考えていた。
加えて、「ランナー飯」という枠組みは出来つつあるものの、そのポジションを取れている食品がまだなかった。「ランナー飯といえば」のポジショニングまで考えた上での発案だった。
この根拠を説明するとメンバーも納得の表情となり、ターゲティングに合わせてコンセプトも「ガチガチの筋トレ層」向けではなく、有酸素運動を中心としたトレーナーに向けたコンセプトで提案をしていく方向に固まったのだった。
提案書を作っていく中で、吉岡は「沼」の膨大な資料を思い出していた。澤田の熱意や時間を思うと、全く新しいターゲットとコンセプトを了承してもらえるのかという不安、そして少々胸の詰まるような思いがあった。
一方澤田は、賭けに出ていたのだろう。同時期、「沼」に似たコンセプトの競合商品が一足先に別の会社から発売されたこともあり、心中穏やかでない中で澤田は東京にいる人たちの感覚に任せることが最善だと判断した。
こうして、「おいしいから始めるヘルシーなカラダづくり」をコンセプトにした栄養食品、「PFC Standard」が作られ始めたのだった。
ECで販売するより前に「Makuake」での事前販売をする提案が通ったことにより、メンバーは10月1日の販売に向けて各々動き始めていた。
都内の数少ない木々に止まっている蝉の声が鈍くなってきた夕暮れ時、生ぬるいような風に押されながら、相原、吉岡、林の三人は行きつけの居酒屋へと向かっていた。
経営者目線の相原、ユーザー目線の吉岡、現実的な視点の林。この三人は意見がぶつかることが多く、行きつけの串焼き屋はいつからか意見交換の場となっている。
「実際入社してみてどう?」
結露し始めたグラスから垂れる水滴をおしぼりで拭きながら、相原は吉岡に訪ねた。串焼き屋には相変わらずの人の入りで、質問に付近のサラリーマンの声が混じる。
質問に端的に答えた吉岡は、一息吸った後「私、思ってたんですけど」と続けた。
「もう少し、プロジェクトに対して前のめりになった方が良くないですか」
少々の沈黙が生まれたのを感じた。だが、吉岡はプロジェクトが進むにつれてクライアントとの関わり方が構えの姿勢であることに、違和感を抱いていたのは事実であり、もう少しアクティブに対応し、熱量を持つべきでないか、と考えていた。
入社したばかりの、歳も下の自分が、会社のトップの立ち位置である二人に生意気なことを言っていると思われないだろうか、とも思った。しかし二人の反応は、そんな心配を安堵に変えるような、素直な頷きと言葉であった。
やはりこのメンバーでよかった、と思えたのもつかの間、販売に向けて獅子奮迅のメンバーに、度重なるトラブルが起こることとなる。
九月の二週目に設定をしたMakuakeでの告知開始まで数週間となっていた頃、ブランド名の決定、パッケージデザインの決定から撮影、製作したLPも何度も作り直し、毎日試食を重ね、普段の業務ではやることのないであろう値段設定までも並行して行い、携る全ての人がまさにてんやわんやという状態だった。
まさか、ネット広告代理店に入社して原価計算から「50円値上げするとどうなるか」を考えて頭を抱えることになるとは思ってもなかったであろうメンバーは徐々に、期日に間に合うか、不安が募っていた。
スケジュールが右往左往する中で、プロジェクトに関わっていたメンバーが離脱するトラブルが起こった。誰にも予想し得ないことだったが、吉岡はより一層気を引き締め「私が今倒れたら終わりだ」と、相原に在宅での業務継続を相談していた。
チャット越しの相談でも切羽詰まった様子が感じ取れた相原だったが、一人だけ在宅の対応をするわけにはいかず、会社全体を在宅業務に切り替えることとなる。それほどまでに、このプロジェクトでの吉岡の存在は大きく、なくてはならない存在だったのだ。
在宅に切り替えた後も、LPとリーフレットを納得がいくまで作り直し、プレスリリースやSNS周り、LINEなどの集客から広告まで、アートディレクター、デザイナー、新卒の社員を含めたメンバー、そして富山にいる澤田たちのチームが、自分の担当すべき部分をやり抜いていた。
このメンバーがいる。それはやはり吉岡にとっては、在宅でも安心して業務に着手できるほどの信頼となっていた。
プロジェクトが始まってからというものの、季節を感じる間もないほどのスピード感で物事が進み、冷房が社内を冷やし始めたのもいつからだったか、記憶には薄い。
吉岡の集めたアンケート結果を持って、プロジェクトメンバーによるターゲティング再考の会議が行われた日は、無理矢理吐き出したような冷房の音がよく聞こえるほどに、主要メンバー五人の雰囲気は落ち着いていた。 各々自分の考えたターゲットを口にしている中で、「ランナー。」と吉岡が呟いた。この発案にも様々な理由が詰まっている。
まず一つに、次々と澤田の工場から送られてくる試作品の一品の量の満足感だった。いわゆるダイエッターに向けて満足感のあるものを売るのではなく、しっかりと食事の量を取りながらも消化や栄養面を気にかけるランナーにアプローチすることを考えていた。
加えて、「ランナー飯」という枠組みは出来つつあるものの、そのポジションを取れている食品がまだなかった。「ランナー飯といえば」のポジショニングまで考えた上での発案だった。
この根拠を説明するとメンバーも納得の表情となり、ターゲティングに合わせてコンセプトも「ガチガチの筋トレ層」向けではなく、有酸素運動を中心としたトレーナーに向けたコンセプトで提案をしていく方向に固まったのだった。
提案書を作っていく中で、吉岡は「沼」の膨大な資料を思い出していた。澤田の熱意や時間を思うと、全く新しいターゲットとコンセプトを了承してもらえるのかという不安、そして少々胸の詰まるような思いがあった。
一方澤田は、賭けに出ていたのだろう。同時期、「沼」に似たコンセプトの競合商品が一足先に別の会社から発売されたこともあり、心中穏やかでない中で澤田は東京にいる人たちの感覚に任せることが最善だと判断した。
こうして、「おいしいから始めるヘルシーなカラダづくり」をコンセプトにした栄養食品、「PFC Standard」が作られ始めたのだった。
ECで販売するより前に「Makuake」での事前販売をする提案が通ったことにより、メンバーは10月1日の販売に向けて各々動き始めていた。
都内の数少ない木々に止まっている蝉の声が鈍くなってきた夕暮れ時、生ぬるいような風に押されながら、相原、吉岡、林の三人は行きつけの居酒屋へと向かっていた。
経営者目線の相原、ユーザー目線の吉岡、現実的な視点の林。この三人は意見がぶつかることが多く、行きつけの串焼き屋はいつからか意見交換の場となっている。
「実際入社してみてどう?」
結露し始めたグラスから垂れる水滴をおしぼりで拭きながら、相原は吉岡に訪ねた。串焼き屋には相変わらずの人の入りで、質問に付近のサラリーマンの声が混じる。
質問に端的に答えた吉岡は、一息吸った後「私、思ってたんですけど」と続けた。
「もう少し、プロジェクトに対して前のめりになった方が良くないですか」
少々の沈黙が生まれたのを感じた。だが、吉岡はプロジェクトが進むにつれてクライアントとの関わり方が構えの姿勢であることに、違和感を抱いていたのは事実であり、もう少しアクティブに対応し、熱量を持つべきでないか、と考えていた。
入社したばかりの、歳も下の自分が、会社のトップの立ち位置である二人に生意気なことを言っていると思われないだろうか、とも思った。しかし二人の反応は、そんな心配を安堵に変えるような、素直な頷きと言葉であった。
やはりこのメンバーでよかった、と思えたのもつかの間、販売に向けて獅子奮迅のメンバーに、度重なるトラブルが起こることとなる。
九月の二週目に設定をしたMakuakeでの告知開始まで数週間となっていた頃、ブランド名の決定、パッケージデザインの決定から撮影、製作したLPも何度も作り直し、毎日試食を重ね、普段の業務ではやることのないであろう値段設定までも並行して行い、携る全ての人がまさにてんやわんやという状態だった。
まさか、ネット広告代理店に入社して原価計算から「50円値上げするとどうなるか」を考えて頭を抱えることになるとは思ってもなかったであろうメンバーは徐々に、期日に間に合うか、不安が募っていた。
スケジュールが右往左往する中で、プロジェクトに関わっていたメンバーが離脱するトラブルが起こった。誰にも予想し得ないことだったが、吉岡はより一層気を引き締め「私が今倒れたら終わりだ」と、相原に在宅での業務継続を相談していた。
チャット越しの相談でも切羽詰まった様子が感じ取れた相原だったが、一人だけ在宅の対応をするわけにはいかず、会社全体を在宅業務に切り替えることとなる。それほどまでに、このプロジェクトでの吉岡の存在は大きく、なくてはならない存在だったのだ。
在宅に切り替えた後も、LPとリーフレットを納得がいくまで作り直し、プレスリリースやSNS周り、LINEなどの集客から広告まで、アートディレクター、デザイナー、新卒の社員を含めたメンバー、そして富山にいる澤田たちのチームが、自分の担当すべき部分をやり抜いていた。
このメンバーがいる。それはやはり吉岡にとっては、在宅でも安心して業務に着手できるほどの信頼となっていた。




まだ目の開ききらない朝、カーテンから差し込む日差しとPCの発する光をほぼ同時に浴び、首回りのストレッチを行う。背伸びをしながら、吉岡はいつも通りプロジェクトのチャットに目を通し始めた。
Makuakeでの事前告知を予定していた期日が刻々と近づき、メンバーの努力により着々と準備が進む中、一通のチャットに思わず目を疑った。 「依頼していた梱包業者の製造メーカーが倒産したらしく」
その後にも文字は並んでいたものの、最初の一文を何度も目で往復することで精一杯だった。納品までに一ヶ月の予定でスケジュールを組んでいたものの、これでは予定通りに進まないどころか、告知開始に間に合わない。
新しい梱包業者を探すにも、すぐには見つからないだろう。テーブルの上に降りかかる日差しは、吉岡の心境とは裏腹に、煌々と輝いていた。
一方、ひたすら商品の改良を続ける澤田にも、相当の焦りが同じく生まれていた。
別の会社と手を組んで一度失敗していたこともあり、「沼」という商品への熱意は、社員から理解を得られずにいた。それでも、コンセプトを変更しPFC Standardをより良いものにするためと、大きい鍋で澤田が一人商品を改良していく姿に、徐々に離れていた社員たちも協力的になっていたところだった。
原材料に使用していた材料の輸入が、取引先で終了することとなったのだ。
栄養バランスを考え抜いた上で選んだ材料の仕入れができなくては、製造も何もできない。新しい代替品を見つけても、栄養成分の確定から味の調整まで、また一から進めないといけない。
そしてそれを、相原たちのチームに伝えないといけない。
相原と澤田のチャットルームでは、最初の印象からは想像もつかないような澤田からの声が、小さく溢れていた。
「もし上手く売れなくても、大丈夫なんで、気にせず」
無理もない。諸々のトラブルで、別の業務にまで影響し、梱包や製造どころか、サイトの開設さえも予定通りにはできなくなっていたからだ。
澤田は商品が売れるかわからない不安の中、ここまでの時間をかけて社員の理解を得て、「お金をかけすぎでないか」と言われることもある中で、相原たちへの信頼の大きさに全てを委ね、互いができる最大の努力をしてきたのだ。
だからこそ相手を気遣う気持ちからの発言だったが、相原の返答は強気なものだった。
「僕らは売るつもりなので、そんなこと言わないでください。PFC Standardは、売れます。」
本気だった。相原たちは、度重なる改良品の試食会ごとに、売れる自信を持っていた。というのも、素直に商品が美味しく、そして栄養面やカロリー面も申し分ないと思っていたからだ。
澤田のスマホにその通知が行く頃には、プロジェクトメンバーはすでに再起動を始めていた。澤田の信頼に応えるように。
Makuakeでの事前告知を予定していた期日が刻々と近づき、メンバーの努力により着々と準備が進む中、一通のチャットに思わず目を疑った。 「依頼していた梱包業者の製造メーカーが倒産したらしく」
その後にも文字は並んでいたものの、最初の一文を何度も目で往復することで精一杯だった。納品までに一ヶ月の予定でスケジュールを組んでいたものの、これでは予定通りに進まないどころか、告知開始に間に合わない。
新しい梱包業者を探すにも、すぐには見つからないだろう。テーブルの上に降りかかる日差しは、吉岡の心境とは裏腹に、煌々と輝いていた。
一方、ひたすら商品の改良を続ける澤田にも、相当の焦りが同じく生まれていた。
別の会社と手を組んで一度失敗していたこともあり、「沼」という商品への熱意は、社員から理解を得られずにいた。それでも、コンセプトを変更しPFC Standardをより良いものにするためと、大きい鍋で澤田が一人商品を改良していく姿に、徐々に離れていた社員たちも協力的になっていたところだった。
原材料に使用していた材料の輸入が、取引先で終了することとなったのだ。
栄養バランスを考え抜いた上で選んだ材料の仕入れができなくては、製造も何もできない。新しい代替品を見つけても、栄養成分の確定から味の調整まで、また一から進めないといけない。
そしてそれを、相原たちのチームに伝えないといけない。
相原と澤田のチャットルームでは、最初の印象からは想像もつかないような澤田からの声が、小さく溢れていた。
「もし上手く売れなくても、大丈夫なんで、気にせず」
無理もない。諸々のトラブルで、別の業務にまで影響し、梱包や製造どころか、サイトの開設さえも予定通りにはできなくなっていたからだ。
澤田は商品が売れるかわからない不安の中、ここまでの時間をかけて社員の理解を得て、「お金をかけすぎでないか」と言われることもある中で、相原たちへの信頼の大きさに全てを委ね、互いができる最大の努力をしてきたのだ。
だからこそ相手を気遣う気持ちからの発言だったが、相原の返答は強気なものだった。
「僕らは売るつもりなので、そんなこと言わないでください。PFC Standardは、売れます。」
本気だった。相原たちは、度重なる改良品の試食会ごとに、売れる自信を持っていた。というのも、素直に商品が美味しく、そして栄養面やカロリー面も申し分ないと思っていたからだ。
澤田のスマホにその通知が行く頃には、プロジェクトメンバーはすでに再起動を始めていた。澤田の信頼に応えるように。




暑さも峠を越え、帰宅時の風は心地良いほどになっていた。去年よりも夏が長引いているような感覚に今年も襲われ、SNSでの「秋、まだ?」という投稿に強く共感していると、流れてくる投稿に「PFC Standard、めっちゃ満足感ある。美味しい」と、もう何度も見た商品名が流れてくる。
九月も終わりを迎えようとしている頃、Makueke販売開始前日。告知期間のメンバーのSNSからの拡散とサイト完成後の地道なギフティング作業により、商品の口コミが集まっていた。
様々なトラブルからの壮絶な再起動により、予定していた九月の二週目にこそ間に合わなかったものの、一週間の遅れをもってMakuakeの事前告知が行われていた。
吉岡は、ポジティブなメンバーと「なるようになる」と前向きだった澤田の、販売日を待つ姿勢に気持ちは救われつつも、一人不安を拭いきれずにいた。結果として告知はうまくいっているものの、大幅に告知期間が短くなっている。
加えて、明日のMakuake開始初日は、会社の創業10年を記念した創業祭を兼ねた内定式でもあった。この不安が残る気持ちで、果たして創業祭に望めるのだろうか。
創業祭の準備をする社員を見ながら、会社を後にした。
「乾杯!」
司会を務める社員の気合の入った掛け声に合わせ、新入社員も含めた社員全員がグラスを上に掲げた。ただし、吉岡一人を除いて。
午前九時に予定していたスタートは、トラブルにより創業祭スタートの正午と被ることとなった。その結果、心配性の吉岡は創業祭をしているオフィスの隅で、最終告知の確認や広告配信の確認、各々のSNSへの配信とダイレクトメッセージの送付など一人パソコンと向き合って淡々と行なっていのだ。
距離の離れた富山では、販売開始にカーソルを合わせた画面を澤田含む社員が、緊張の眼差しで見守っていた。一息の間の後、クリックの音が静寂の中響いた。
内定者が作ってきたゲームを社員が笑い混じりで行う中、眉をしかめて画面を見ていた吉岡の顔が徐々に喜びと安堵が混じった表情に変わっていくのを見て、数人のプロジェクトメンバーもパソコンの画面の横に集まってきた。
一分に一個の速さで、リターンが購入されている。その事実は、吉岡の数々の抱えていた不安をかき消すような数字として、ページをリロードするたびに更新されていく。
増える購入の数、それと同時に、チャットの通知が短く鳴った。送信相手は澤田だった。
「注文のメールが止まりません!」
澤田は、使い古したスマホの充電が注文のメールの多さにより減る中で、同時に販売者としての責任を感じ始めていた。やっとここまできた。そんな感覚に浸っている暇もなく準備や購入の対応に追われながらも、自分が作り続けてきた商品が歩き始めた事実に喜びを噛み締めた。
自分の心から溢れた喜びをプロジェクトチームへ届けたその一通のチャットは、吉岡がリロードするたび増えて行く数字に、尚現実味を帯びさせる。
盛り上がっている様子のメンバーを見て、代表として「創業祭に集中してほしい」と一度注意をしていた相原でさえも、その頃にはパソコンの画面に釘付けとなっていた。
販売開始から54分、ほとんどのメンバーが飛び交う笑い声の中に戻っていた中、吉岡の繰り返しリロードしていた指が一瞬、止まった。
「達成、してる」
残っていた相原と吉岡が目を見合わせ、手を握って互いを激励したのも束の間、相原の大声で発された達成報告により、創業祭の中にあった声達が祝福の声へと変わる。
その声と鳴る拍手は、少数精鋭のメンバーが注いできた時間をゆっくりと汲み取るように、創業祭の会場を響かせていた。
九月も終わりを迎えようとしている頃、Makueke販売開始前日。告知期間のメンバーのSNSからの拡散とサイト完成後の地道なギフティング作業により、商品の口コミが集まっていた。
様々なトラブルからの壮絶な再起動により、予定していた九月の二週目にこそ間に合わなかったものの、一週間の遅れをもってMakuakeの事前告知が行われていた。
吉岡は、ポジティブなメンバーと「なるようになる」と前向きだった澤田の、販売日を待つ姿勢に気持ちは救われつつも、一人不安を拭いきれずにいた。結果として告知はうまくいっているものの、大幅に告知期間が短くなっている。
加えて、明日のMakuake開始初日は、会社の創業10年を記念した創業祭を兼ねた内定式でもあった。この不安が残る気持ちで、果たして創業祭に望めるのだろうか。
創業祭の準備をする社員を見ながら、会社を後にした。
「乾杯!」
司会を務める社員の気合の入った掛け声に合わせ、新入社員も含めた社員全員がグラスを上に掲げた。ただし、吉岡一人を除いて。
午前九時に予定していたスタートは、トラブルにより創業祭スタートの正午と被ることとなった。その結果、心配性の吉岡は創業祭をしているオフィスの隅で、最終告知の確認や広告配信の確認、各々のSNSへの配信とダイレクトメッセージの送付など一人パソコンと向き合って淡々と行なっていのだ。
距離の離れた富山では、販売開始にカーソルを合わせた画面を澤田含む社員が、緊張の眼差しで見守っていた。一息の間の後、クリックの音が静寂の中響いた。
内定者が作ってきたゲームを社員が笑い混じりで行う中、眉をしかめて画面を見ていた吉岡の顔が徐々に喜びと安堵が混じった表情に変わっていくのを見て、数人のプロジェクトメンバーもパソコンの画面の横に集まってきた。
一分に一個の速さで、リターンが購入されている。その事実は、吉岡の数々の抱えていた不安をかき消すような数字として、ページをリロードするたびに更新されていく。
増える購入の数、それと同時に、チャットの通知が短く鳴った。送信相手は澤田だった。
「注文のメールが止まりません!」
澤田は、使い古したスマホの充電が注文のメールの多さにより減る中で、同時に販売者としての責任を感じ始めていた。やっとここまできた。そんな感覚に浸っている暇もなく準備や購入の対応に追われながらも、自分が作り続けてきた商品が歩き始めた事実に喜びを噛み締めた。
自分の心から溢れた喜びをプロジェクトチームへ届けたその一通のチャットは、吉岡がリロードするたび増えて行く数字に、尚現実味を帯びさせる。
盛り上がっている様子のメンバーを見て、代表として「創業祭に集中してほしい」と一度注意をしていた相原でさえも、その頃にはパソコンの画面に釘付けとなっていた。
販売開始から54分、ほとんどのメンバーが飛び交う笑い声の中に戻っていた中、吉岡の繰り返しリロードしていた指が一瞬、止まった。
「達成、してる」
残っていた相原と吉岡が目を見合わせ、手を握って互いを激励したのも束の間、相原の大声で発された達成報告により、創業祭の中にあった声達が祝福の声へと変わる。
その声と鳴る拍手は、少数精鋭のメンバーが注いできた時間をゆっくりと汲み取るように、創業祭の会場を響かせていた。




皆が二次会へと足を運ぶ中、吉岡は、日の暮れたオフィスの街並みを一人履き慣れたスニーカーを鳴らして帰路に付いていた。
どっと気力と体力が抜けたような感覚の上で、心はこれから始まるECでの販売への準備を始めていた。
まだこれからだ。
吉岡は、慣れた手つきで明日の朝七時のアラームをセットし、ポツポツと賑わい始めた串焼き屋の横を通り過ぎる。きっとまたここで、あの三人と顔を合わすだろう。
トレーニングでも初めてみるか、そう思った自分が少し可笑しくて、数ミリ、口角を上げた。
どっと気力と体力が抜けたような感覚の上で、心はこれから始まるECでの販売への準備を始めていた。
まだこれからだ。
吉岡は、慣れた手つきで明日の朝七時のアラームをセットし、ポツポツと賑わい始めた串焼き屋の横を通り過ぎる。きっとまたここで、あの三人と顔を合わすだろう。
トレーニングでも初めてみるか、そう思った自分が少し可笑しくて、数ミリ、口角を上げた。
SERVICES & PRODUCTS
事業領域・提供サービス
-
デジタルマーケティング伴走支援
データ分析から具体的な施策実行まで、お客様のマーケティング活動を継続的に支援いたします。内製・アウトソース問わず柔軟に対応し、実効性の高い打ち手をご提案します。
詳細を見る -
ランディングページの制作と運用
13年間で1,000件以上の実績を持つLP制作。広告との連動性を重視したCVR向上をご提案します。競合優位性を表現するコピーライティングと運用改善で成果を最大化します。
詳細を見る -
広告ソリューション
ビジネス目標から逆算した戦略的な広告運用で、持続可能なROI向上をお手伝いします。高度なデータ分析と運用力で、デジタルマーケティング全体の成功を導きます。
詳細を見る -
データサイエンス
複雑なデータを分かりやすく整理し、売上向上に直結する具体的な改善策をご提案します。単なる可視化ではなく、経営判断に活用できる実用的なデータ環境を構築します。
詳細を見る -
Magic LPO
AI技術でWebサイト改善案を自動提案。ノーコードで迅速なCVR向上を実現します。専門アナリストのサポートにより、人材不足の課題も解決いたします。
詳細を見る -
ノーコードツール「Click」
記事LPやスワイプLPなど、あらゆるコンテンツ型ランディングページを直感操作で制作可能です。診断コンテンツやAIチャットボットまで、圧倒的な低コスト・高速で量産いただけます。
詳細を見る
CONTACT
お問い合わせ
マーケティングに関するご相談
- 現状のデジタルマーケティング戦略を見直したい
- 広告運用を改善したい
- データ分析やデータ基盤の構築について相談したい
- ブランドデザインについて相談したい





